 わたしの1冊グランプリ「ほんシェルジュ大賞」
わたしの1冊グランプリ「ほんシェルジュ大賞」
「ほんシェルジュ大賞」決定!
11月4日(月曜日・振替休日)に名古屋市公会堂で開催された読書フェスティバル会場にて、「ほんシェルジュ大賞」が決定・発表されました。
受賞作品は、投票総数830票のうち、最も得票数の多かったエントリーNo.2 『よい子への道』(おかべりか/作 福音館書店)の紹介文です。
たくさんの投票をいただき、ありがとうございました。
最終集計結果は下記PDFファイルからご覧いただけます。
☆ 「ほんシェルジュ大賞 最終集計結果」<PDF形式 262KB>
![]()
PDF形式のファイルを閲覧するにはAdobe Reader(無料)が必要です。
※AcrobatReader5.0以上を推奨しています。
わたしの1冊グランプリ「ほんシェルジュ大賞」に投票してください!
名古屋市図書館全21館では、約120名の司書「ほんシェルジュ」が、日頃より図書館の利用方法や資料について市民の皆様にご案内を行っています。その「ほんシェルジュ」による本の紹介文のコンテストを開催します。
ほ んシェルジュが書いた本の紹介文を読んで、「この本を読んでみたくなった!」と思う紹介文に投票してください。最も得票の多い紹介文を「ほんシェルジュ大 賞」として決定し、11月4日(月曜日・振替休日)の読書フェスティバル会場で発表します。投票の対象となる紹介文10点は、ほんシェルジュ全員による事 前の内部選考を経て選ばれた優秀作です。ほんシェルジュがこれまでの人生で出会った、とっておきのおすすめから、お気に入りの一冊を見つけ、ぜひ投票して ください。
優秀作10点の紹介文は「ほんシェルジュ大賞」ノミネート作品をご覧ください。また、優秀作を掲載した冊子を各図書館で配布します。投票いただいた方の中から、抽選で5名の方に記念品を差し上げます。
- 投票できる方: 名古屋市図書館共通貸出券をお持ちの方
- 投票期間: 10月1日(火曜日)~10月31日(木曜日)
- 投票方法: 名古屋市立図書館全21館で受け付けます。また、図書館ホームページからも投票できます。
*11月4日(月曜日・祝日)開催の「読書フェスティバル」当日も会場(名古屋市公会堂)で投票を受け付けます。(投票時間:午前10時30分~午後1時) - お問合せ: 名古屋市鶴舞中央図書館 TEL:052-741-3131
※投票受付は終了しました。
「ほんシェルジュ大賞」ノミネート作品
「ほんシェルジュ大賞」優秀作10点の紹介文です。
- 【1】『100均フリーダム』
- 【2】『よい子への道』
- 【3】『図書館が教えてくれた発想法』
- 【4】『ああ息子』
- 【5】『建築探偵東奔西走』
- 【6】『生まれてバンザイ』
- 【7】『さわる文化への招待 触覚でみる手学問のすすめ』
- 【8】『ヒーローを待っていても世界は変わらない』
- 【9】『金鯱の夢』
- 【10】『陶淵明全集 上・下』
| 【1】 『100均フリーダム』 | |
 |
内海慶一/著 ビー・エヌ・エヌ新社 |
| おせっかいな本があふれている。 お金持ちになるには、人付き合いが上手になるには、好きな人と結婚するには。 こんなにも多くの人たちが、こんなにも多くの角度から幸せになる方法を伝授してくれているのに、どうしてわたしたちは未だに幸せになれないのだろう、と思って愕然とする。 そんな中ごくまれに、何かの事故としか思えない本が紛れ込んでいることがある。本書がその筆頭だ。 100均グッズの魅力を写真と文で紹介した本。いわゆる「まともな」商品は掲載されていない。用途不明の道具や、きもちわるいオブジェが次々と登場する。著者はそれらへの愛を、もったいないほど多くの語彙を駆使して熱く語る。 どうでもいい。心底どうでもいい。 でも、気がつくと顔がにやけている。 本を読んで手に入る幸せなんてそのくらいでいい。他人の決めた幸せの定義に惑わされるな。そんな深いメッセージがこめられている、というわけでは特にないのが本書の魅力。 (南陽図書館 ほんシェルジュ 石谷睦美) |
|
| 【2】 『よい子への道』 | |
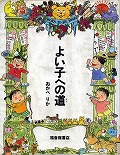 |
おかべりか/作 福音館書店 |
| いつの時代も、子どもたちは、「よい子」になるために、苦労しています。いやいや、もうすっかり大きくなった大人たちだって、やっぱり 「よい子」でいるのは、辛い!会社や学校で「よい子」でいようと思うと、いろんなものが、胸の内やお腹の中にたまって、とても身体に悪そうです。 そんな時、どうすればすっきりして明日も元気に会社や学校へ行けるのでしょうか。ちょっと一杯やってストレス解消とはいかない20歳未満のあなた、そして、もともとお酒の飲めないあなた、是非この本を読んで下さい。 この本に載っている、よい子になるためにあなたがしてはいけないことの数々を、読み進んでいけば、もう抱腹絶倒!大笑いした後は、気がつけば気分はなんだかすっきりです。でも、決して電車の中では読まないように。 (守山図書館 ほんシェルジュ 小山 妙) |
|
| 【3】 『図書館が教えてくれた発想法』 | |
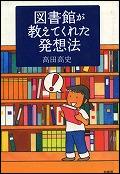 |
高田高史/著 柏書房 |
| 「ああ、そうよ。そうなのよ。」が、かつてこの本を読んだ時の思いである。なにが"そう"なのか?それは、司書としての発想法である。簡 単に内容を紹介すると、図書館でアルバイトをすることになった彩乃さん(若い女性である)が、司書である職員から、調べ物のコツを教えてもらうというも の。私自身が司書であるので、その内容が目新しい訳ではない。しかし、そこには、図書館員の調べ物という作業が、明解に(しかもユーモアをもって)文章化 されていたのである!「うんうん。私はこういうことをしている(あるいは、したい)のね。」それは、難しい調査方法とかではなく、ちょっとしたコツ。でも、この本に書かれている発想法と知識を身につければ、図書館での調べ物に、きっと役に立つはず。この本は、私にとって「実は図書館って、こんなところなんですよ。」と、たまに誰かに手渡したい衝動にかられる、そんな1冊なのである。 (鶴舞中央図書館 ほんシェルジュ 山田淳子) |
|
| 【4】 『ああ息子』 | |
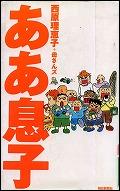 |
西原理恵子+母さんズ/著 毎日新聞社 |
| わが家には息子がいる。この子は幼い頃から大変だった。雨の日も風の日も外へ行きたがるので、雨にも負けず風にも負けず母はベビーカーを押した。まるで放牧である。しかし牛や羊なら夜は終了なのだが、ヤツは夜も散歩へ行きたがった。昼寝をすれば無限のエネルギーにリセットされてしまうのだ。その結果、夜の散歩に使ったアンパンマンのゴーゴーカーのタイヤは、ひび割れてしまった。 小学1年生の時、ひらがなの「み」がわからなくな り、母が国語の教科書を見なさいと言うと、「みーみーみー、みーんみんみんみんみー」とセミに化けて逃走してしまった。 ああ、息子よ。そんな毎日の心の なぐさめは、『ああ息子』である。男子を持つ全国の母親必読の書だと信じている。「息子を育てているうちに子育てのこころざしが異常に低くなっている事に 気づく。死ななきゃいいとか」。これが心の支えである。 (南図書館 ほんシェルジュ 小垣弥生) |
|
| 【5】 『建築探偵東奔西走』 | |
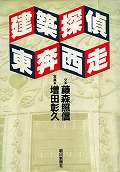 |
藤森照信/文 朝日新聞社 |
| 出会いにはタイミングがある。それは本の場合も例外ではない。十代の頃に出会っていたら、私は建築家を目指したに違いない。残念なことに、出会った時にはすでに就職しており、なおかつ文系一筋の人生を歩んできたため、かなわぬ夢であった。 私 の人生を変えそこねた本とは、『建築探偵東奔西走』をはじめとする藤森照信氏の建築探偵シリーズである。藤森氏は、近代建築の謎を読み解き、どんな建物に も歴史とドラマがあることを読者に教えてくれる。その鮮やかな語り口はまさに探偵!すっかり魅了された私は、他の著書に手をのばし、現地に赴き、気がつけ ば、レンガやアーチを見てはにやにやするアヤシイ人になっていた。明治村に行ったことをきっかけに本書を手に取ったのだが、それ以来、どこに行っても建物 が気になる。ある意味、私の人生を変えたのもしれない。惜しいことに、現在、書店では入手できない。図書館では読めるので、ぜひ。 (鶴舞中央図書館 ほんシェルジュ 中谷有希) |
|
| 【6】 『生まれてバンザイ』 | |
 |
俵万智/作 童話屋 |
| 思わず手に取りたくなる本、というのがあります。手になじむ小さなサイズ、柔らかい背の丸み、にじんだ暖かい色の表紙...この本がまさしくそうでした。初めての育児に奮闘していた頃、ふっとひかれるように手に取りました。 当時、子どもが食べない泣きやまないなど、ささいなことで右往左往しては情報を求めて片っ端から本を開きました。タレントさんの優雅な育児本、小児科の先生のアドバイス本、くすっと笑える育児漫画...。その中で、いちばん心をラクにしてくれたのがこの本でした。 『サ ラダ記念日』で一躍有名となった歌人の俵万智さんが、母となって詠んだ短歌が1ページに一首ずつ収められています。子どもの成長の瞬間を切り取った歌は、 子育ての幸せの記録でもあると思います。小説とは違って、好きなところから好きなだけ読んで楽しめるのも短歌ならではの魅力です。 肩の力を抜いてまた明日もがんばろう、そう思わせてくれる小さくても頼もしい本です。 (鶴舞中央図書館 ほんシェルジュ 島田佳織) |
|
| 【7】 『さわる文化への招待 触覚でみる手学問のすすめ』 | |
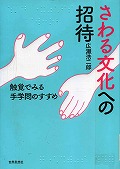 |
広瀬浩二郎/著 世界思想社 |
| 人は情報の八割を目から得るといわれています。私も著者と同じ中途失明の障害者です。視覚以外の四感を駆使しながら日々生活しています。 紙に打ち出されたでこぼこに触れて文字を読み、握った杖の先で段差を確認し、指先をとおして湯呑みの温もりを感じます。こうした何気ない日常の、「さわ る」という行為を一つの文化として紹介してくれたのがこの本です。そして、私に「さわる」ことへの奥深さを改めて教えてくれました。 著者は、冒頭 で「「さわる文化」「手学問」の広くて深い世界を全盲者の専有物にしたくない。健常者といわれる人たちにも体験可能な普遍性を持っており、目の見える方々 にこそぜひ味わってほしいものなのだ。」と書いています。私たちは、触れて感じて自由に想像を膨らませていきます。読者の皆さんは、「さわる」ことによってどんな新たな世界が生まれてくるのでしょうか。いままで気づかなかった何かが見つかるかも!! (鶴舞中央図書館 ほんシェルジュ 大塚 強) |
|
| 【8】 『ヒーローを待っていても世界は変わらない』 | |
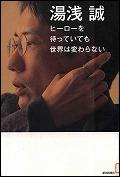 |
湯浅誠/著 朝日新聞出版 |
| 意見が全く違う他人とかかわるのは結構疲れる。理解を得るのはもっと大変だ。つい誰か影響力のある人(ヒーロー)に頼み、その人に全てを 委ねてしまいたくなるかもしれない。だけど身の回りでいつもそんなうまい具合に事が運ぶとは限らない。日本社会全体ではなおさらだ。著者の湯浅誠さんは、 通すべき自分の意思があるならば、しんどくても反対意見を持つ人との意見調整を自分自身で行う必要があると言う。「民主主義」とはそういうことなのだ。 余 裕がある人しかそれはできないって?もともと野宿者(ホームレス)の人々が抱える生活の問題を始め、余裕のない人の各種の貧困問題に取り組んできた湯浅さ んはそんな反論は百も承知だ。彼は、周囲がしんどいことに取り組めるだけの余裕(時間と空間)を社会の皆で協力して作り上げていくべきだと主張する。それ は巡り巡って自分にも帰ってくる。 余裕(のなさ)を自分だけの問題じゃなく、社会の問題として捉える著者の視点は、自分の閉塞感を軽くしてくれると同時に、他者と社会に向き合うための新たな方法を与えてくれた。 (瑞穂図書館 ほんシェルジュ 川嶋章平) |
|
| 【9】 『金鯱の夢』 | |
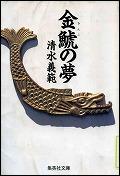 |
清水義範/著 集英社 |
| 「1603年 豊臣幕府 名古屋に成立!!」徳川でなく豊臣将軍家による名古屋時代260年の繁栄を謳(うた)う大河歴史(!?)小説で ある。江戸時代をまるごとパロディにしているので、江戸夏の陣で徳川は滅び、「忠臣蔵」刃傷事件の舞台は名古屋城松の廊下、幕末には鞍馬天狗でなく大曾根天狗が活躍する。ちなみにペリーの黒船は浦賀でなく師崎に来航した。この「名古屋時代」のその後を記す最終章は、一般人用と愛知県人用の2種類用意され、 結末が違っている。どちらに共感するかで「名古屋愛」を試されてしまうので、是非、読み比べていただきたい。私が大阪の高校生だった頃、この本や同じ作者の『蕎麦ときしめん』に感化された。まるで海外の日本アニメファンが日本という聖地に焦がれるが如く、「名古屋」は、私にとってマルコ・ポーロが目指すジパングとなった。その結果、名古屋の大学を受験し、名古屋の図書館で働いている。人生の半分を名古屋で暮らしているのは、この本のおかげであり、この本の せいでもある。 (徳重図書館 ほんシェルジュ 藤本昌一) |
|
| 【10】 『陶淵明全集 上・下』 | |
 |
陶淵明/[著] 岩波書店 |
| 功利的な読書は、何かさもしい。無用の用という言葉がある。無用な読書もいいかもしれない。 本書は、古代中国4、5世紀の頃の詩人の作品集。役人務めにいやけがさし、郷里の田園に隠遁。自ら農作業に従事し、貧しい中でも、酒に親しみ、飲酒の詩を多くつくった。これを読むと、酒を飲まないのに、陶然と酔う心地がする。桃源郷のもとになる作品もつくった。そのユートピアへは、二度と訪ねることができないことで、想いはさらに募る。その他、人口(じんこう)に膾炙(かいしゃ)した詩は多く、口ずさむだけでも、心地よい。これらを読んでも何も役立つことはない。しかし、それを読んで陶然とした時間は、何にもかえられない至福の時だろう。至福の時を持ったという記憶は、宝石のように輝く。この宝石をたくさん持つということは、きっと人生を豊かにしてくれる。これは、逆説的だが、無用が用になることではないか。 (緑図書館 ほんシェルジュ 宇佐見幸弘) |
|
紹介文は下記PDFファイルからもご覧いただけます。
☆ 「ほんシェルジュ大賞 優秀作10点」<PDF形式 743KB>
![]()
PDF形式のファイルを閲覧するにはAdobe Reader(無料)が必要です。
※AcrobatReader5.0以上を推奨しています。

