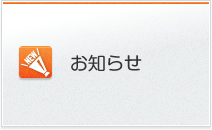展示期間:2025年6月21日(土曜日)から9月18日(木曜日)
現在放送中のNHK大河ドラマ『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺』
日本のメディア産業、ポップカルチャーの礎を築き、時にお上に目を付けられても面白さを追求した人物、"蔦重"こと蔦屋重三郎の波乱万丈の生涯を描いたドラマです。(公式HPより)
ドラマでは多くの人が読書を楽しむ様子が出てきますが、ここ尾張名古屋でも読書文化が栄えていました。
今回の展示では、当時の尾張の読書文化を支えていた貸本屋や書林(出版元)などに関連する資料をご覧いただきます。
※なんでも調査団報告書 No.150「尾張の出版」(外部リンク)
※名古屋の偉人伝 18「江口惣八」(外部リンク)
※名古屋の偉人伝 38「片野東四郎」(外部リンク)
■ 主な展示資料 ■
| No. | 書名 | 著者名 | 出版者 | 出版年 | 分類 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 文会書庫扁額 | 尾張藩士で晩年には"書物奉行"も勤めた河村秀穎が安永2(1773)年に創立した「文会書庫」に掲げられた扁額です。文会書庫は河村家で収蔵していた書籍を広く一般に公開し、尾張の読書文化の発展になくてはならない存在でした。江戸時代の"本の虫"たちも見ていたであろう、由緒深い扁額です。 | ||||
| 2 | 大惣貸本店図 | [名古屋市鶴舞中央図書館(製作)] | 2004 | A018 | 大惣は明和4(1767)年に名古屋で開業した貸本屋です。坪内逍遥が母親に連れられて大惣を訪れているところを想像して描かれたというこの絵は、山田秋衛(1888~1968 名古屋生)によって描かれ、昭和27年8月に戦後のバラック建てから新装開館した鶴舞図書館に記念として贈られたものと伝えられています。 | |
| 3 | 尾陽商工便覧 | 川崎源太郎/編 | 国書刊行会 | 1986 | A670 | 明治21(1888)年に刊行された『尾陽商工便覧』に「東壁堂永楽屋片野東四郎」が掲載されています。開業から約100年、大店になり繁盛している店先の様子が描かれています。もともと本だけではなく、薬や墨も扱っていましたが、4代目の頃には呉服屋も兼営していたことが分かります。 |
![]()
PDF形式のファイルを閲覧するにはAdobe Reader(無料)が必要です。
※ AcrobatReader5.0以上を推奨しています。