こんげつの本
本のなまえや表紙をクリックすると、貸し出し中かどうかなどがわかります。
※表紙の画像掲載に関する著作権の許諾については、出版社の許可をいただいております。
「これがはじまり」の本
『しおふきうす』
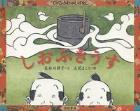
長谷川摂子/文
立花まこと/絵
岩波書店
どうして、うみのみずがしおからいか、しっている?
うみのそこに、しおをふきだしつづけている、ふしぎないしうすがあるからなんだって。
どうして、いしうすがうみのそこにしずんでいるのかというと、ね。
『いろいろへんないろのはじまり』
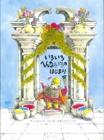
アーノルド・ローベル/作
牧田松子/やく
冨山房
ずっとずっとむかし、このせかいに「いろ」はありませんでした。
すべてがくろか、しろか、はいいろで、このころのことを「はいいろのとき」といいました。
けれでも、いま、せかいはいろいろないろにあふれています。それは、あるまほうつかいのおかげなのです。
まだまだあるよ、「これがはじまり」の本
| 本のなまえ | かいたひと・出版社 | 紹介 |
|---|---|---|
| 世界のはじまり | メイヨー/再話 ブライアリー/絵 百々佑利子/訳 岩波書店 |
人間は火を使います。火のおかげで、寒い冬をあたたかく過ごし、食べ物をあたためることもできます。 けれども、昔むかし、火は、高い山のてっぺんにかくされていました。 かしこいコヨーテは、かわいそうな人間に火をやろうと考え、動物たちによびかけました(「うけとれ、走れ!」)。 世界のはじまりのおはなしが10話のっている本です。 |
| はじまりはたき火 | 火とくらしてきたわたしたち | まつむらゆりこ/作 小林マキ/絵 福音館書店 |
おはなしの世界では、動物たちが人間に火をもたらしてくれました。 では、実際はどうだったのでしょう。 わたしたちのくらしにかかせないエネルギー。明るさやあたたかさ、食事をとるための火から始まって、石炭(せきたん)、蒸気(じょうき)機関(きかん)、石油(せきゆ)、電気(でんき)へとエネルギーのもとは変(か)わってきました。 その歴史(れきし)とこれからを考えさせられる絵本です。 |
| かえるの竹取ものがたり | 俵万智/文 斎藤隆夫/絵 福音館書店 |
『竹取物語』は、『源氏物語』で「物語の出きはじめの親」と紹介され、日本最古の物語といわれています。 「かぐや姫」でおなじみですが、しっかりと読んだことがある人は少ないのでは? 登場人物をかえるにおきかえた、ユーモラスな絵本で、日本の物語のはじまりを味わってみませんか。 |
| グーテンベルクのふしぎな機械 | ジェイムズ・ランフォード/作 千葉茂樹/訳 あすなろ書房 |
むかし、本は手書きでした。 手で書き写していたので、本を作るのには、手間と時間がかかりました。 1450年ごろ、グーテンベルクは金属の活字と印刷機を使って、本を印刷しました。 それ以降、印刷機はヨーロッパ中に広まって、たくさんの本が印刷されるようになりました。 グーテンベルクの機械は本の歴史をかえたのです。 |
| はじまりの樹の神話 (こそあどの森の物語 6) | 岡田淳/著 理論社 |
スキッパーはこそあどの森のウニマルという家に住んでいます。 ある夜、スキッパーのもとに、しっぽが光ってことばをしゃべるキツネがやってきました。 そして、死にそうな子が森にいるから、スキッパーに助けてほしいと言うのです。 |