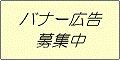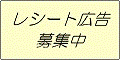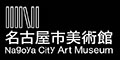図書館 蔵書検索・予約システム
このページは ○○○図書館の 共通部分 ページです。
言語選択メニュー
文字サイズや言語を切り替えます。
ログインの状態:ログインしていません。ログインすると利用状況の確認等のサービスを利用できます。 |
カート(予約候補) 0 登録されていません。 |
機能を切り替えます。
いろいろ検索のメニューです。
ここから本文です。
感染拡大防止のため、本を読む前、読んだ後は手を洗いましょう。みなさまのご協力をお願いします。
感染拡大防止のため、本を読む前、読んだ後は手を洗いましょう。みなさまのご協力をお願いします。
本文はここまでです。
Copyright © 2008 Nagoya City Library. All rights reserved.
アクセシビリティについて | 個人情報の取り扱いについて | ソーシャルメディアアカウント運用ポリシー | 免責事項について | サイトマップ | お問合せ先
ページの終わりです。